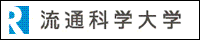共同研究
1.未来の教室をめざして-ICTの利用活用による教育の現状と課題について-
研究者一覧
| 研究者 | 所属大学 | |
|---|---|---|
| 代表者 | 井内 善臣 教授 | 兵庫県立大学 |
| 秋吉 一郎 教授 | 兵庫県立大学 | |
| 藤本 健司 准教授 | 神戸市立工業高等専門学校 | |
| 多井 剛 准教授 | 流通科学大学 | |
研究発表テーマ
未来の教室をめざして-ICTの利用活用による教育の現状と課題について-
研究概要
(1)研究の背景・動機
電子黒板の導入や学校のインターネット接続に加え、ネットブックやiPadなどの高機能タブレット型端末などが出現し、ICT利活用による教育のあり方が盛んに議論されている。さらに、ネットワークの高速化、無線LANやスマートフォンの急速な普及など「真の情報通信革命」が始まろうとしている。 文部科学省中央教育審議会が平成24年8月28日に出した「文部科学省中央教育審議会答申」の中で「新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて~生涯学び続け、主体的に考える力を育成する大学へ~」を謳っており、この中では、とりわけ学修時間への「こだわり」が取り上げられている。文科省令大学設置基準では45時間の授業内容をもって1単位と定めており、通常大学で行われる授業では、半期、週1回(1.5時間)の授業では15回の授業回数で2単位としているケースがほとんどである。したがって2単位の科目であれば学修時間は90時間(45時間×2単位)となるが、実際に教室内で行われる授業時間は22.5時間(1.5時間×15回)である。しからば残りの67.5時間(90時間-22.5時間)は教室外での「予習」や「復習」を想定していることになる。つまり週1回(1.5時間)の授業に対して、「2.25時間の予習」と「2.25時間」の復習が毎回課されていることになる。この学修時間の条件を満たすための教育環境を大学としては整備・提供する必要に迫られている。 また、教材コンテンツをいかにして教員自身が容易に短時間で作成、配信できるかということに関して、携帯端末特有の操作性の問題や教材開発アプリケーションの少なさ、教員のこうした教育方法への抵抗感など、いくつかの困難さに直面をしている。 今や教育分野におけるICTの利用は必然的であり、それにともなって教育支援の形態や教育方法も変革してきている。 本研究の目的は、①携帯端末やパソコンなどICT利活用による教授法、②教育環境の整備、③電子教材、教育コンテンツについて、の3つの視点から、先進事例や技術動向の現状を調査すると同時に、学生の知的潜在能力を引き出すための大学教育の質的転換の重要性に着目をし、個々人の能力に応じた教育コンテンツや学習方法の提供、学習管理、教育環境の整備など、未来の教室、教育法のあるべき姿について、議論、提案することである。
(2)研究実績・成果
目標に掲げた3つの視点から「現状と動向」や「先進事例」について情報収集や事例調査を実施した。
①ICT利活用による教授法
主体的、能動的学修を積極的に進めるためには、これまでの「講師から学習者への一方的教授」でなく、「講師と学習者の双方でのコミュニケーション」あるいは、「学習者どうしの学び合い(互学互修)」の重要性を誰もが認めていることである。
また、これまでのように教室での「説明型の授業」でなく「反転授業」つまり、あらかじめ学習内容を宿題(調べ学習)とし、教室では、その成果を元にグループ学習やアクティブラーニングを行ったりすることにより、より主体的学習能力を養おうとする教授法の有用性が求められている。
②教育環境の整備
学修時間の確保のひとつの考え方として「教育環境のシームレス化」ならびに「主体的、能動的環境の教室整備」が必要となろう。多くの教育現場ではこうした視点から「アクティブラーニング教室」とこれに連動をした「ラーニングコモンズ」の整備や「Mooc(Massive Open Online Courses:大規模公開オンライン講座)」への取り組みが行われている。
「シームレス化」とは「空間を超えた連続的思考」と「世代間を超えた時間的学修」の意味であるととらえることができる。
また、図書館の果たす役割の一つとして「知の拠点」としての図書館の役割が見直されている。これまでは静寂な環境で図書の閲覧を行い、知的レベルを高めるだけの図書館の役割から「グループ学習」や「互学互修」のための知の拠点となりつつある。
われわれは、本研究目的を遂行するために、いくつかの大学・高等教育機関で現在、提案されている「ICT利活用による教育」の実態調査やいくつかの企業から提供されるICT利活用における「未来型教室」の事例調査を行い、精査した上でその評価を行った。
③電子教材、教育コンテンツ
デジタル教科書、電子教材など文字のデジタル化については百花繚乱の状況であるといわざるを得ない。各社がそれぞれの手法でデジタル化を進めており、また、それを取り巻く周辺の技術についても標準化されていない。ある程度の時を経て標準化が進んで行く、いわゆるデファクトスタンダード(事実上の標準化)が進んでゆくものと予想される。また、デジタル化の過程やデジタルの特性から「著作権」課題も浮上しており、法律面での整備も急がれるところである。
(3)今後の展望
ユビキタスネットワーク社会の実現を迎えてシームレスな教育環境は充実していると言えよう。有線、無線にかかわらず「いつでも、どこでも、だれでも、なんでも」アクセス可能となっている。クライアント側のハードにも大きな制約はなく、パソコンをはじめ、タブレット、ケータイ・スマートフォン等々、多様な機器に対応ができる。単純にいえば「教室型机の配置」や「黒板とチョーク」のことばに代表されるような従来型教育環境は「自由なレイアウトが可能な教室」や「デジタル教材」など「フューチャー教室」へと変化してゆくであろう。しかし、課題もいくつか浮かび上がってきている。こうしたICT技術に対応した教員の情報スキル、また、その育成法、教材の開発、および開発支援、環境の整備など、数多く存在する。もっとも大きな課題は教える側、つまり教員や教育に関わる人たちの「意識改革」が必要である。
他機関等への研究成果発表予定 兵庫県立大学 商大論集に成果発表予定
Strict Standards: Non-static method CCalendar::GetCalendar() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CHtmlBuilder.php on line 217
Strict Standards: Non-static method CCalendar::GetWeekday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 129
Strict Standards: Non-static method CCalendar::GetMonthDays() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 130
Strict Standards: Non-static method CCalendar::GetMonthDays() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 131
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
カレンダー
阪神淡路大震災資料集
加盟大学

UNITY(Academic Community Hall)
Kobe Academic Park Association for the Promotion of Inter-University Research and Exchange
Copyright © 1994 - 2025 UNITY. All Rights Reserved. -- このサイトについて
This page is produced by Kobe City College of Technology.