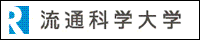共同研究
2.イノベーションと企業の経営形態:新技術の開発と利用に関する一研究
研究者一覧
| 研究者 | 所属大学 | |
|---|---|---|
| 代表者 | 三上 和彦 教授 | 兵庫県立大学 |
| 田中 悟 教授 | 神戸市外国語大学 |
研究発表テーマ
イノベーションと企業の経営形態:新技術の開発と利用に関する一研究
研究概要
(1) 研究の背景
社会におけるイノベーション(技術革新)の担い手は、誰であるべきなのか。この問いに対する経済学の標準的な答えは、次の通りであろう。新しい技術には公共財的な側面がある。したがって、専有することが困難であるか、または不適切であるような基礎的技術の開発は公的機関や非営利組織が担当する。そして、専有が容易な応用研究については、営利企業が担えばよい。
しかし、近年のイノベーションについて言うと、この役割分担は必ずしも成り立っていない。例えば、バイオテクノロジーや情報・通信技術の分野では、営利企業が基礎的技術の開発に従事する一方、公的な機関が応用技術の開発に経営資源を投入するといった事例も決して珍しいものではない。こうしたことから、今日、従来の単純な二分法によって望ましいイノベーターの姿を描写することは、必ずしも適切ではないものと思われる。
これまで、三上(研究代表者)と田中(研究分担者)は、それぞれ「企業の経営形態」と「イノベーション」をキーワードに、個別に研究を行ってきた。そうした両者の知識を交流させることにより、今日における望ましいイノベーターの姿について何らかの見解を見出すことができるのではないだろうかというのが、この共同研究のそもそもの発端であった。
(2) 研究実績・成果
イノベーションを考えていく上で、まず押さえておかなければならないことは、それにかかる費用の負担の問題である。一般企業の場合、イノベーションにかかる費用は研究開発費として計上される。研究開発費は、新製品の開発や既存製品の改良などを通して、将来の企業収益の増加に寄与することが期待される出費である。これは、製造費や販売管理費などと異なり、企業収益に直接結び付いているものではない。その意味で、研究開発費は、経済学で言う埋没費用として位置づけるのが適切である。私たちは、まず、この埋没費用の存在が、企業の経営形態にどのような含意を持つのかについて検討した。
次に、一口にイノベーションといっても、様々な種類のイノベーションが存在する。新製品の開発、より効率的な組織編成に関するアイデア、あるいは新しい社会制度の構築など、その幅は広い。その中で私たちが注目したのが、医療分野におけるイノベーションである。病院の経営形態は、(1)公的病院、(2)民間非営利病院、(3)民間営利病院、の3つに大別できる。それぞれの形態の病院の市場シェアは国によって異なるが、各国に共通して言えることは、医療分野は他の産業に比べて、公的セクター及び民間非営利セクターの占める割合が極めて高い、ということである。これについては、ある程度、従来の二分法による説明が当てはまりそうに思われる。すなわち、(広い意味での)医療技術の公共性である。しかし、他の要因も考えられる。すなわち、より一般的な立場からいえば、医療の質に関する情報の非対称性の問題が大きいのではないかと考えられる。私たちは、こうした問題を、経済理論の枠組みの中で検討した。
(3) 今後の展望
正当な順序から言えば、これまで私たちが行った研究は理論的なものであり、まだ仮説の段階のものである。今後は、現実のデータ等を用いるなどして、実証的な面からの検証を行っていく必要がある。
しかし、私たちは、データ等を用いた実証研究に入る前に、まだ押さえていかなければならない理論的な課題も少なくないものと考えている。その一つとして、非営利組織の本質に関する理論研究がある。イノベーションの分析に限らず、非営利組織の経済学的研究においては、まず非営利組織が存在するところから議論が始まり、他の形態の事業体との比較が行われる。しかし、これは、ある意味で、重要な問題をスキップしているものともいえる。すなわち、そもそもなぜ市場経済(あるいは資本主義経済)に非営利組織が出現するのか、という疑問である。
共同研究班としての期間は終了するが、今後もこうした問題を正面から捉え、本研究課題を進展させていきたいと考えている。
Strict Standards: Non-static method CCalendar::GetCalendar() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CHtmlBuilder.php on line 217
Strict Standards: Non-static method CCalendar::GetWeekday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 129
Strict Standards: Non-static method CCalendar::GetMonthDays() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 130
Strict Standards: Non-static method CCalendar::GetMonthDays() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 131
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
カレンダー
阪神淡路大震災資料集
加盟大学

UNITY(Academic Community Hall)
Kobe Academic Park Association for the Promotion of Inter-University Research and Exchange
Copyright © 1994 - 2025 UNITY. All Rights Reserved. -- このサイトについて
This page is produced by Kobe City College of Technology.