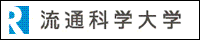共同研究
4.学校連携によるアートワークショップを通じた地域づくり
研究者一覧
| 研究者 | 所属大学 | |
|---|---|---|
| 代表者 | 曽和 具之 准教授 | 神戸芸術工科大学 |
| 小野原 教子 准教授 | 兵庫県立大学 | |
研究発表テーマ
学校連携によるアートワークショップを通じた地域づくり
研究概要
- 山と海に囲まれたみなと街「神戸」
兵庫県神戸市。関西の中心的都市大阪に隣接し、人口約150万人の都市である。古くから貿易港として発展し、奈良時代(AC. 710?794)の頃から、中国(宋・明)をはじめ諸外国との貿易拠点として栄えた。 わずか半年足らずではあるが、当時の首都がおかれたこともある*1。
その後、江戸時代(AC. 1603-1867)に入り鎖国政策などで外国貿易は一時途絶えるが、1672年に国内航路(西廻り航路)が整備されることにより、天下の台所・大阪の外港として栄えた。 そして、1868(慶応3)年の兵庫開港により、再び対外国貿易都市となった。
1889(明治22)年に市制が施行された当時の人口は約13万人。その後、周辺市町村との合併によって、1941(昭和16)年には約100万人を擁する都市へと発展した。天災や戦争などで一時期人口は減少したが、 1960年代の高度経済成長に支えられ、国際的貿易都市として発展した。
1995(平成7)年に阪神・淡路大震災により甚大な被害を受けた。都市基盤となるインフラや道路・公共施設などの復興は進んでいるが、市では引き続き暮らしのサポートを進め、復興計画推進プログラムを策定、 市民・事業者・市が協同で早期の本格復興をめざして取り組みを進めている。 - 神戸市のニュータウン開発と学園都市
高度経済成長期に日本各地で行われたニュータウン開発は、神戸市においても1970年代から盛んに行われてきた。海と山が近接した神戸においては、平野部が少ない。このため神戸市では、大規模なニュータウンを 開発するために、山を切り開き、その土砂を用いて海を埋め立てることによって、広大なニュータウンおよび商・工業用地を確保してきた。1985(昭和60)年には、神戸市西部の山林の土砂を用いて造成された、 ポートアイランド*2において、地域博覧会が開かれ、未来都市のあり方を世界にむけて提唱した。その後、六甲アイランド*3、神戸空港*4などの人工島を造成した。
神戸研究学園都市(神戸市西区。図1。以下、学園都市)は、神戸市の都市開発の一環として造成された街である。総面積約330ha、人口約15,000人。小学校や中学校などをはじめ、高校・短大・大学・専門学校など 12校が隣接する学校集中地域である。また、学園都市がある地域は、かつて山林と田畑が広がる丘陵地帯であり、現在も農業が営まれている。また、近隣には1300年の歴史を持つ寺院などを有する旧集落がある。 - 地域性を活かしたまちづくり
2004年、国際都市としての歴史を持ち、かつ近隣には山林や田畑が残り、古い歴史を持つ学園都市において、小学校・中学校・高等学校・大学および地域が連携したアートワークショップ「学園都市学校連携アートワーク ショッププロジェクト」を実施することになった。この地域活動の中心を担ったのは、神戸芸術工科大学、および兵庫県立伊川谷北高等学校(以下、伊川谷北高校)*5、そして、近隣の小学校に通っている児童の保護者などである。
3-1 ワークショップの構造
2004年10月に第1回目のワークショップを行い、2010年までに計7回実施している。参加者は毎年、約100名。スタッフ約50名によるアートイベントである。実施したアートワークショップの基本理念は、「子どもと高校生、大学生、そして地域の人々が協同して1日で作品を仕上げる」ことにある。すなわち、有名なアーティストを招いて子どもたちにアートの教育をするのではなく、 また、家庭や学校に持ち帰り何日もかけて仕上げるものでもない。朝、会場に集まり、テーマを聞き、それぞれの役割をその場で決めて、作業にかかる。そして、夕方には展示をするという、即戦力と協調性を必要とする作業である。
3-1-1 ON STAGE(表舞台)
限られた時間内で、年齢層、知識、経験の異なる世代がスムーズに活動し、かつ学んだ内容を的確に理解できるようにするため、このワークショップでは、大きく3つの階層に分けてそれぞれの作業に従事している。ON STAGEは、子どもたちが中心になってアート活動をする場である。ここでは、子どもたちは教えられて行動を起こすのではなく、自発的に自分たちの役割を見いだしながら行動していくことが求められる。
3-1-2 BACK STAGE(裏舞台)子どもたちの自発的な活動を支えるために、BACK STAGEの高校生および大学生スタッフは、単に色の塗り方や、線の引き方を教えるのではなく、協同で制作する作品へのかかわり方を子どもたちに気づかせるよう導くことが求められる。 「教える」のではなく「導き出す」ことがスタッフに求められるため、サポートスタッフのことを「ファシリテータ*6」と呼称している。
3-1-3 META STAGE(俯瞰台)
また、限られた短い時間内で一定の成果を出すためには、子どもたちやファシリテータが自らの活動を常に振り返ることができるような環境を整備することが重要である。BACK STAGEには、ワークショップ内で起こっている 現象をデジタルカメラやムービーで克明に記録し、即座に編集、開示する作業が要求される。このため、記録・編集専用のスタッフおよび必要機材を会場に配置している。現場において刻々と状況の変わるワークショップにおいては、全体をしながら、子どもたちの活動内容や、最終完成に向けてのファシリテータへの指示、記録スタッフへの編集確認などを行う必要がある。 META STAGEのスタッフには、全体を把握しながら、常にワークショップの方向性を決定する能力が要求される。
3-2 地域とのかかわり方このアートワークショップのもう一つの重要な理念に、「地域との密接なかかわりによる活動」がある。このワークショップを通して、子どもたちだけではなく、スタッフや保護者などが、地域のアイデンティティを 見いだすことができるようにすることが求められる。また、地域にある資源を地域の人々の協力のもとに収集し、ワークショップで活かしていくことで、歴史ある従来の町の人びととニュータウンに暮らす人びとが、 自発的に地域作りに参加できる環境を構築することも、この活動の重要な要素となっている。
- アートワークショップの実施
ここでは、2010年9月に実施された第7回学園都市学校連携アートワークショッププロジェクトを例に、学校と地域の連携について述べていく(図1)。
図1 第9回学園都市学校連携ワークショッププロジェクト 第7回のアートワークショップでは、水彩絵の具、蛍光塗料および蓄光塗料を用いて彩色を行った造形物を制作した。参加した小学生は2年生から6年生までの約120名。小学生が造形をしやすいように、 想像上の生物の形態をモチーフに制作を展開した。
造形物はその日のうちに会場内に展示した。近隣の農家から提供していただいた稲わら・茅などを古代の学園都市に見立てて、子どもとスタッフ全員で展示作業を行った。また、夜間は紫外線ライトを照射し、 蛍光塗料および蓄光塗料の効果を発揮できるようにした。4-1 子どもの感性のおもむくままに
このワークショップでは、子どもたちの感性を最大限に生かし、その感性によって引き起こされる創作へのパワーを高校生および大学生のスタッフによって造形物に仕上げていくことが目的である。 そのため、できる限り制作に制限を与えず、子どもたちの作るがままに任せるようにした。そして、形の整形や色彩構成など、子どもたちが制作の途中で迷ったときに、高校生および大学生が助言を与えるようにした。
その結果、最終成果物にさまざまなバリエーションが生まれ、また、子どもたちは成果物に対して、強い関心を寄せるようになった。4-2 記録とリフレクション
4-1で述べたように、このワークショップでは最終成果物に対して優劣をつけたり、あるいは模範成果物を展示したりすることはなかった。そのため、子どもたちが制作プロセスで、いかに楽しみ、集中し、 かつ感性を解き放って制作活動に没頭できたかを客観的に観察する必要があった。そこで私たちは、ワークショップ中の記録を動画と静止画で綿密に記録し、会場内で子どもたちに開示していった。 このことにより子どもたちは、数分前に自分たちがしていた行動を客観的に観察することができるようになり、自分たちの制作に対する姿勢やスタッフなどとのコミュニケーションについてリフレクション*8をすることが可能になった。
4-3 Webサイトによる公開
記録されたデータは即日webサイトに掲載され、参加者が帰宅後に1日を振り返ることができるよう考慮した。これにより、ワークショップを1日限りのイベントとするのではなく、次回の参加を喚起させたり、 あるいは、次の参加の時にはさらに制作意欲が向上した状態で臨めるように配慮した。
- 地域に根ざした学校教育を目指して
今回のワークショップの特徴の一つとして以下の点が上げられる。
- (1)地域の小学校・中学校・高等学校・大学および地域住民が一体となってイベントの準備、進行を担った。
- (2)ニュータウンの住民と周辺集落の住民とのかかわりを持たせるため、素材の一部に周辺地域の野山から採集した稲わらや茅を用いた。
- (3)子どもたちに制作活動を通じて、地域の歴史や環境を学び取ってもらうために、制作だけでなく、展示準備や後かたづけも共同で行った。
特に、(2)については、周辺地域の協力があってこそ成り立った活動であった。日常生活の中で、ほとんど分離した環境におかれているニュータウンと周辺集落の住民にとって、このような活動を通して、 情報を交換できたことはこれまで数少なかったように思われる。単に目新しい制作活動を繰り広げるのではなく、地域に内在する人的・物質的・地理的環境を考慮しながら、地域に根付いた活動を続けていくことが、 これからの地域活動にとって重要であると考えている。
引用文献
*1.福原京:治承4年(AC. 1180)6?11月。現在の兵庫区に設置*2.第1期:1966年着工、1981年竣工、総面積436ha。第2期:1987年着工、2005年竣工、総面積390ha
*3.着工:1972年、居住開始:1988年、総面積580ha
*4.2006年開港
*5.神戸市西区学園西町6-1。1986年開校。文系・理系・芸術系の雄コースに分かれてカリキュラムを構成。
*6.facilitate v. ~を容易にする。facilitator n. ~を容易にする人
*7.reflection n. 沈思, 熟考, 熟慮;《哲》反省などの意味を持つ。ワークショップなどを行った際に自分の発言や行動について顧みながら次の行動を起こすきっかけとする行為の意味として用いられる。
参考文献
1.曽和具之、住民主体の「かかわり」のみえるまちづくり、神戸芸術工科大学紀要、2002年p.26-39。2.中西紹一編著、ワークショップ 偶然をデザインする技術、宣伝会議、2006年。
3.野田直人監訳、参加型ワークショップ入門、Robert Chambers著、明石書店、2004年。
4.久保田賢一、水谷敏行編著、ディジタル時代の学びの創出、日本文教出版、2002年。
Strict Standards: Non-static method CCalendar::GetCalendar() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CHtmlBuilder.php on line 217
Strict Standards: Non-static method CCalendar::GetWeekday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 129
Strict Standards: Non-static method CCalendar::GetMonthDays() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 130
Strict Standards: Non-static method CCalendar::GetMonthDays() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 131
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
カレンダー
阪神淡路大震災資料集
加盟大学

UNITY(Academic Community Hall)
Kobe Academic Park Association for the Promotion of Inter-University Research and Exchange
Copyright © 1994 - 2025 UNITY. All Rights Reserved. -- このサイトについて
This page is produced by Kobe City College of Technology.