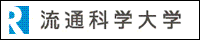共同研究
国際報道における英語の役割
研究者一覧
| 研究者 | 所属大学 | |
|---|---|---|
| 代表者 | 船山 仲他 教授 | 神戸市外国語大学 |
| 三間 英樹 准教授 | 神戸市外国語大学 | |
| 川越 栄子 准教授 | 神戸市看護大学 | |
研究発表テーマ
国際報道における英語の役割
研究概要
日本発のニュースを世界が見る媒体の一つとして、CNN、BBCなどのグローバルネットワークがある。 本研究では、そのようなネットワークに乗った日本のニュースの中で日本人の顔、あるいは声がどの程度露出しているかを、インタビュー形式に注目して観察、分析した。 放送事業者の立場に立つレポーターの報告に対して、インタビュー部分は現地の人間の生の声が世界に伝わる機会となる。 そのような機会を日本人が他の国民、民族に比べてどのように活かしているのか、その際英語という言語がどの程度関与するのか、というような問題について、定性的、定量的な分析を試みた。 資料としては、2008年9月から2009年8月までの1年間にCNNjから放映されたWorld News Asiaという番組を対象とした。 この番組はアジアのニュースを中心にしているので、日本のトピックが取り上げられる可能性が高く、日本のニュースがどのように作られるかを観察する機会も多いことになる。 録画した上で、日本発のニュースにおけるインタビューを頻度、長さ、言語、特質の観点から分析し、さらに、中国、アメリカ発のニュースの場合と比較した。 また、分析対象としたインタビューは、政治家やスターなど特定の人の考え方や生活を掘り下げるようなタイプのものではなく、なんらかの出来事、話題に関する取材の中での証言的なインタビューに限定した。 インタビューは、典型的には1項目3分前後のストーリーの中に位置づけ、次のような時間を計測した。
表:測定した時間| 放送日 | 項目全体 | インタビュー部分 | 発話の出力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 顔 | 別映像 | 肉声 | 英語訳 | |||
| 2009/4/2 | 200” | 59” | 32” | 27” | 52 | 7 | |
| 内訳 | 1-1 | - | 2” | 2” | 0” | 2” | 0” |
| 1-2 | - | 25” | 10” | 15” | 25” | 0” | |
| (省略) | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 6” | 6” | 0” | 1” | 5” | ||
| (省略) | - | - | - | - | - | - | |
この例の場合、数値欄の1行目にあるように、ひとつのニュース項目となるストーリーの長さは200秒で、その中でインタビュー部分が59秒ある。 その間、インタビューされている人の顔が画面に映っているのが32秒、ほかの映像が移っているのが27秒であった。 このインタビュー59秒の内52秒が本人の声、7秒が別人の英語訳であった。 この1行目がこのストーリー全体のまとめであり、その下は内訳である。 全体で59秒あったインタビューの内、1人目の1回目の発話(表では1-1の行)は2秒あり、その間顔は映っており、本人の肉声が聞こえている。 英語訳がなく本人の声が聞こえているということは、この人物は英語を話していることになる。表中1-2の行は1-1と同じ人物が今度は25秒間話していることを表している。 表中、2と表示のある行は、次に別の人のインタビューが6秒あったことを示している。 この人は日本語で答えており、肉声も1秒ほど聞こえているが、その後はレポーターが英語訳を5秒間かぶせている。 この英語訳は、レポーターとは別の人間が流すこともある。 そのような場合、日本の放送では声優が翻訳原稿をせりふのように読むことが多いが、CNNのニュースの場合、職業的通訳者が英語訳をかぶせるのが普通のようである。
このようなデータを基に日本人がインタビューされる場合の特徴を考察した。 まず目立つことは、やはり英語をしゃべらない日本人のアイデンティティが薄れることである。 ニュース番組作りの技法として、頭に1秒前後日本語を聞かせた後、レポーターあるいは通訳者に英語訳をしゃべらせることになるが、必ずしも映画の吹き替えのように口の動きに合わせて英語訳が出てくるわけではないので、顔とことばの一体感が薄れる。 また、インタビューされている人を画面にとどめる限り、視聴者は少なくとも話し手の顔が見えるわけであるが、話す時間が長くなると、他の映像が挿入される傾向にある。 これは日本語原語に限らず、英語原語でも同様であるが、インタビューされている人の顔と肉声の両方が消えてしまうと、やはりしゃべっている人のインパクトが減少すると考えられる。 英語話者の場合、顔が消えても肉声は消えないので、その人のアイデンティティは保たれやすい。 また、英語訳の中では、レポーターでも一人称を使って語る場合もあるが、多くは、三人称の代名詞あるいは人名とsayを組み合わせた言い方になり、英語聴者は日本人発話者からの距離を感じることになる。 そして、内容的に見た場合、通訳されたコメントは簡潔で結論的なものが多く、掘り下げた発言は少ない。 英語で直接語っている場合にはもっと複雑な発言がある。
数値化しにくい特徴として、英語を話せる日本人を探してくる傾向があり、内容的にも、また、英語を日常使っているかどうかという点でも、それが代表的な日本人かどうか、の疑問が残る。たとえば、英語を話せる政治家を好んでインタビューすると、言語以外の選択要因が相対的に低まる可能性がある。 あるいは、車を買いに来ている日本人客が流暢な英語をしゃべっていると、それが一般的な日本人であると言えればいいのだが、現実はどうなのか疑問が残る。 さらに、英語で直にインタビューできることが話題選びにも影響しているのではないかと思われる場合もある。 自閉症の人たちを雇用しているワイン醸成工場の話やラブホテルの経営の話は、その経営者が英語話者であろうとなかろうと話題性があるように思われるが、直接英語で取材できることが選択基準に影響しているようにも思える。
*本研究の成果に基づく論文を『時事英語学研究』などの関連学会誌に投稿する予定である。
Strict Standards: Non-static method CCalendar::GetCalendar() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CHtmlBuilder.php on line 217
Strict Standards: Non-static method CCalendar::GetWeekday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 129
Strict Standards: Non-static method CCalendar::GetMonthDays() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 130
Strict Standards: Non-static method CCalendar::GetMonthDays() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 131
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
カレンダー
阪神淡路大震災資料集
加盟大学

UNITY(Academic Community Hall)
Kobe Academic Park Association for the Promotion of Inter-University Research and Exchange
Copyright © 1994 - 2025 UNITY. All Rights Reserved. -- このサイトについて
This page is produced by Kobe City College of Technology.