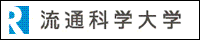共同研究
神戸研究学園都市における当初マスタープランと現状の比較考察~これからの研究教育機関と地域との連携に向けての基礎調査
研究者一覧
| 研究者 | 所属大学 | |
|---|---|---|
| 代表者 | 水島 あかね 助手 | 神戸芸術工科大学 |
| 倉知 徹 助手 | 神戸芸術工科大学 | |
| 早川 紀未 助手 | 神戸芸術工科大学 | |
| 亀屋 恵三子 講師 | 神戸市立工業高等専門学校 | |
研究発表テーマ
神戸研究学園都市における当初マスタープランと現状の比較考察~これからの研究教育機関と地域との連携に向けての基礎調査
研究概要
- 研究の背景・目的
神戸研究学園都市は、昭和51年の新神戸市総合基本計画の中で位置づけられた後、同53年4月の「神戸研究学園都市構想」に基づき開発されたニュータウンである。計画当初には、研究教育機能の整備基本方針として、1)地域主義の思考、2)生涯教育への接近、3)国際性の追求の3つが掲げられていた。しかしながら、現在は幾つかの連携事例はあるものの、当初の目標設定、特に研究機関と地域との連携は計画通りには進んでいないように思われる。一方で、地域連携は今日の研究機関において重要な課題の一つともなっている。また、まちびらきから25年が経過した市街地の再編や、新たな環境整備が必要になると考えられる。そこで本研究は、開発当初の計画を整理分類し、これからの地域社会と研究機関の関係の在り方の考察と、今後の市街地再編に向けた課題抽出を行うことを目的としている。
- 研究実績・成果
研究の方法として、1)入手可能な範囲で計画当時の資料収集・分析、2)現地の現状調査(学園西町・学園東町)や関係者へのヒアリング調査による現状把握を行った。
- 当初の計画での位置づけ・内容
神戸研究学園都市は、昭和40年に策定された「神戸市総合基本計画」の中で位置づけられた「西神ニュータウン構想」に端を発している。その後、昭和 51年策定の「新神戸市総合基本計画の中で研究学園都市の構想が明確化された。神戸研究学園都市はこの中でC地区として計画され、関連施設を含め約 250haの規模で、人口2万人の住宅、神戸の将来の社会的・文化的発展の拠点、文科系・芸術系・工科系・福祉系の各分野を柱とした総合的な学園群とすることとなった。また、研究学園と住宅地とが融合した都市構成を図り、まち全体が研究学園であるような雰囲気を作り出すことを目標とされた。
昭和54年の「神戸研究学園都市計画調査」の中で、神戸研究学園都市の役割と基本方針が示され、土地利用の考え方がまとめられた。神戸研究学園都市の役割は、1)神戸都市圏における研究教育環境・条件の整備充実に資する、2)都市活動・市民生活の向上に結びつく知識・情報センターとする、3)国際港湾都市神戸にふさわしい人材の育成、交流機会の拡大等により進展する国際化への対応を図る、4)地域経済の高度化に資する研究開発機能の強化・充実を図る、5)市民と研究学園関係者の相互交流を促し、新たなコミュニティの形成に取り組む、とされた。また、神戸研究学園都市の基本方針は次の3点とされた。 1)地域主義の指向:神戸における研究教育上の課題に対応し、かけている分野を補いつつ、地域の社会・文化・経済基盤の強化に役立つ人材の育成と指導的拠点となることをめざす。また、地域に根ざした研究教育活動の全国的・国際的展開を期待する。2)生涯教育への接近:生涯教育の視点から新しい研究教育の実験場とするため、専門家、市民の意向を充分取り入れつつ、それを可能にする人材集団を積極的に誘致するとともに、目的に沿った活動がしやすいような環境づくりを行う。3)国際生の追求:国際港湾都市神戸にふさわしい国際感覚と国際的視野を身につけた人材の養成をになうとともに、教育・学術・文化の国際交流の機会拡大に努める。
土地利用では、「研究学園施設地区」と「住宅地区」で構成し、両地区の配置は空間的に一体性をもたせ、両地区利用者の円滑な交流を促すため、「研究学園施設地区」を南北2地区に配し、その中間部に東西2近隣住区からなる住宅地を配置する。また、高速鉄道西神線の駅舎を都市の中心部に設け、これを拠点に各施設地区を有機的に結びつけるゾーンとして「中心街区」を設定した。「中心街区」は、駅舎をとりまく「中心地区」と、都市軸としての「学園通り地区」を持って構成するとした。
- まちびらき以降の変遷
昭和60年に神戸市住宅供給公社住宅への入居開始、高速鉄道西神延伸線開通、小中学校の開校などがあり、神戸研究学園都市のまちびらきが行われた。昭和61年に神戸市外国語大学が移転開校、県立伊川谷北高校が開校、昭和63年に流通科学大学が新設開校、平成元年に神戸芸術工科大学が新設開校、平成2 年に県立神戸商科大学(現県立大学)が移転開校、神戸市立工業高等専門学校が移転開校した。平成8年に神戸市看護大学が開学した。
また、神戸研究学園都市の大学連携では、昭和60年に神戸研究学園都市5大学協議会が発足、平成2年にこれを発展させた神戸研究学園都市大学連絡協議会が発足した。平成10年に大学交流センターの運営のため神戸研究学園都市大学交流センター推進協議会が発足し、大学共同利用施設「UNITY(ユニティ)」が竣工した。さらに平成18年に、神戸研究学園都市大学連絡協議会と神戸研究学園都市大学交流センター推進協議会の二つを発展的に解消し神戸研究学園都市大学交流推進協議会が発足した。
一方、現地の現状調査とヒアリングにより、学園都市の住民の多くが、研究学園都市という教育・研究機関が数多くあることを意識して生活しているとはいえない実態が明らかになった。またUNITYが全国に先駆けた組織であり一定の成果をあげてきてはいるものの、地域住民との連携という点においてはまだ改良の余地があることがわかった。学園都市に一人暮らし・下宿する学生が少ないなど、学生が住みやすい環境が整備されていないことも改めて浮き彫りになった。この様な中、平成7年に阪神淡路大震災が発生したが、計画の遅延や一部変更が見られたが、大きな計画変更はなされていないことも判明した。
これからの学園都市住民と大学関係者(教職員、学生)の相互交流や地域連携を考える上でUNITYの活用(地域に向けた広報など)や学生が町に関われる環境づくりなどが必要といえる。また、当初の構想・計画(マスタープラン)と学園都市の現状との比較から、当初の目標が実現できていない部分(市街地空間)が判明した。
- 当初の計画での位置づけ・内容
- 今後の展望
まちびらき(入居開始)から25年が経過した神戸研究学園都市の今後を考える上で、市街地の再整備と地域連携の取り組みの要素が判明した。今後は、研究課題として神戸研究学園都市の再整備に向けた情報収集を行う必要がある。
なお、この成果は神戸芸術工科大学紀要「芸術工学2010」に発表予定である
Strict Standards: Non-static method CCalendar::GetCalendar() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CHtmlBuilder.php on line 217
Strict Standards: Non-static method CCalendar::GetWeekday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 129
Strict Standards: Non-static method CCalendar::GetMonthDays() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 130
Strict Standards: Non-static method CCalendar::GetMonthDays() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 131
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
カレンダー
阪神淡路大震災資料集
加盟大学

UNITY(Academic Community Hall)
Kobe Academic Park Association for the Promotion of Inter-University Research and Exchange
Copyright © 1994 - 2025 UNITY. All Rights Reserved. -- このサイトについて
This page is produced by Kobe City College of Technology.