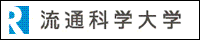共同研究
日中のコミュニケーションギャップ緩和に寄与する日本語と中国語の言語学的分析
研究者一覧
| 研究者 | 所属大学 | |
|---|---|---|
| 代表者 | 下地 早智子 准教授 | 神戸市外国語大学外国語学部 |
| 任 鷹 准教授 | 神戸市外国語大学外国語学部 | |
| 森 宏子 准教授 | 流通科学大学商学部 | |
研究発表テーマ
日中のコミュニケーションギャップ緩和に寄与する日本語と中国語の言語学的分析
研究概要
本研究は、日中両言語話者がより対人関係を構築するために役立つ言語的知識を発掘・提供することを目的とする。
まず、任鷹氏は、日本人の誤りやすい中国語文法について、論理的な側面から検討を加える研究を担当した。本研究班では、日本人の中国語中上級学習者の作文などの多くに見られるエラーのうち、中国語の語順、動詞と目的語のcollocation、 学習者には理解しがたい構造と意味の関係に関わる諸問題について、主に認知言語的見地から、論理的に検討している。
- <動詞的語義特性対共現名詞的指称方式的制約和影響>(動詞の意味特性が名詞句の指示性に与える制約と影響)では、名詞句の定性解釈が、文法的位置だけでは決定されず、動詞の意味特徴との相互作用を考慮しなければならないことを、生成語彙意味論などの観点を用いて具体的に明らかにしている。
- <従「V上」「V下」的対立与非対立看語義拡展中的原型効応>(V上とV下の対立と非対立からた意味拡張におけるプロトタイプ効果)では、“上”“下”という対立する意味を持った移動動詞と、それが複合動詞の第二成分となる場合について、意味が対立する場合としない場合の例について、 「プロトタイプ効果」という認知意味論の概念を用いて整理・説明している。
- <動詞詞義在結構中的游移与実現―兼議動賓結構的語義関係問題>(構造内において生じる動詞の意味の変異と実現―動目構造の意味関係の問題の議論を兼ねて)では、共起する名詞句や構造全体が、動詞の意味に変異を生じさせる現象について論理的な検討を行っている。
- <「这本書的出版」分析中的幾個疑点―従『“这本書的出版”与向心結構理論難題』説起>(“这本书的出版(この本の出版)”分析に見られるいくつかの問題点――「这本书的出版(この本の出版)”と内心構造理論の難題」より) では“这本书的不出版”(この本を出版しないこと)という構造の存在によって“这本书的出版”における“出版”が「名詞化」していないとする従来の議論には理論的に不備があることを指摘し、中国語文法における品詞論の特異性を論じている。
森宏子氏は、教科書の中国語や文章表現には表れないが、中国人同士の日常会話には頻繁に用いられる言語要素の談話的役割について分析を加える研究を担当した。本研究班においては、第二人称代名詞の談話用法について分析している。
- 「虚構的指示における二人称代名詞“你”」 “你”は、二人称すなわち「聞き手」の指示が本分であるが、“你”の中には明らかに「聞き手」を指示しないものがある。本研究では、まず、中国語では “你”が一般論を導く仮説的主語と用いられる場合があることを観察する。そして、この種の“你”の拡張用法として 「私」を隠し、私個人の私的な体験を一般論として提示するために機能する用い方が存在することを主張している。
下地早智子は、日本人と中国人が相互に誤解しやすい言語要素について、対照言語学的分析を加えること、及び研究統括を担当した。
- 「中国語の条件文における副詞“就/才”の役割―コピュラ文の解釈を手掛かりに―」と(5)「也淡“就”“才”与句末“了”的隐现问题」では、上級学習者にも頻繁にエラーが生じる副詞“就”“才”と“了”の共起関係について、ネイティブスピーカーの語用例を素材として分析を加えた。
- 「日本語と中国語のコピュラ文について」では、「は」や「が」のような助詞が存在しない中国語において、指定文と措定文のような違いがどのように表現されているかを観察・分析した。
- <语法现象里视点用法的日汉差异――直指性移动动词、被动表述以及时态/时制的情况>(日中両語における文法現象としての視点の差異)では、移動動詞、受け身、時制の表現について、日本語と中国語に見られる用法のずれが、すべて両言語において、話し手が事態を観察する視点の違いとして説明できる可能性を論じた。
- 「日中の言語行動に関する対照研究:今まで誤解してました」では、2007年度下地研究室所属ゼミ生と共同で、日本人と中国人の間で誤解の生じやすい言語行動に関する先行研究を収集するとともに、研究史を概観した。
Strict Standards: Non-static method CCalendar::GetCalendar() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CHtmlBuilder.php on line 217
Strict Standards: Non-static method CCalendar::GetWeekday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 129
Strict Standards: Non-static method CCalendar::GetMonthDays() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 130
Strict Standards: Non-static method CCalendar::GetMonthDays() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 131
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
カレンダー
阪神淡路大震災資料集
加盟大学

UNITY(Academic Community Hall)
Kobe Academic Park Association for the Promotion of Inter-University Research and Exchange
Copyright © 1994 - 2025 UNITY. All Rights Reserved. -- このサイトについて
This page is produced by Kobe City College of Technology.