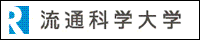共同研究
社会の期待に応える英語教育を構築するための調査
研究者一覧
| 研究者 | 所属大学 | |
|---|---|---|
| 代表者 | 川越 栄子 助教授 | 神戸市看護大学 |
| 野村 和宏 教授 | 神戸市外国語大学 | |
研究発表テーマ
社会の期待に応える英語教育を構築するための調査
研究概要
英語教育の変革期において、社会がどのような英語力を備えた人材を必要としているかを研究することは大変重要であり急務であると考え、英語に対する社会のニーズを調査するため企業を中心にアンケート調査を実施し分析した。全国の一部上場企業から業種・規模に偏りがないように無作為抽出した企業の社員 500名を対象として人事担当者にアンケート調査を送付し回答の協力を依頼した。回答数は45と全体の9%と予想を大きく下回ったが、この中からもある程度の傾向が浮かび上がっている。主な調査項目および結果の概要は以下のとおりである。
- 英語使用度
仕事の中で英語を使用する頻度に関して、読む、書く、話すという作業別に、毎日、週1度以上、2週間~1ヶ月に1度、2ヶ月~6ヶ月に1度、7ヶ月から1 年に1度、ほとんどない、という選択肢を与えて回答を得た結果である。1年に1度以上を合計した結果は次のとおりである。
- 「読む」
項目 結果 A E-メール 48.9% B 英文報告書 24.4% C 英語論文 8.9% D インターネット 35.6% E 新聞・雑誌 20.0% - 「書く」
項目 結果 A E-メール 35.6% B 英文報告書 20.0% C 英語論文 4.4% D 英文手紙 26.7% - 「話す」
項目 結果 A プレゼンテーション 20.0% B 講演 2.2% C 電話 44.4% D 会議 15.6% E 日常会話 24.4%
ここでの結果に現れたメールの読み書き、インターネット上の英語を読むといった項目が多くなっていることは、パソコンやインターネットを通してビジネスが行われることが普通になっている現状では納得できることである。読む作業の中では英文による報告書、英字新聞等を読むことがそれに続き、英語論文そのものを読むことは全体からみれば、それほど多いことではない。
書く作業では英語のメールを書くことと同様にパソコンなどを用いた作業と考えられるが、英文手紙を書くこと、英文報告書を書くことがそれに続き、やはりここでも英語論文を書くことが求められることは全体からすれば少ない。もっとも企業の業種・職種によれば、新技術を海外に向けて一刻も早く発信するために英語論文を書くことが必要となるところもあると考えられる。あくまでも今回の調査からは英語論文を読む、書くといった仕事内容は少ないということである。
話す方では英語で電話対応することが一番多く、次に日常会話、そしてプレゼンテーション、会議と続き、英語で講演を行うという頻度は非常に少ないことが分かった。
- 「読む」
- 職種別による英語必要度および大学教育に取り入れる必要度
企業の職種別に英語に関する仕事内容がどの程度必要とされるかを調査した。またそれぞれの項目を大学における英語教育で取り入れる必要性について質問した。選択肢は、絶対必要、必要、あまり必要ない、必要ない、の4つを用意し、ここでは絶対必要、必要とした数字を表にまとめる。
事務職 営業職 技術職 研究職 大学教育に取り入れる必要性 一般文章を読む 60.0% 57.8% 64.4% 73.3% 84.4% 業務関連(専門的)文章を読む 37.8% 37.8% 53.3% 62.2% 51.1% 一般文章を書く 55.6% 48.9% 57.8% 68.9% 80.0% 業務関連(専門的)文章を書く 33.3% 35.6% 53.3% 64.4% 48.9% プレゼンテーション 20.0% 42.2% 44.4% 57.8% 64.4% 一般英会話 64.4% 64.4% 66.7% 71.1% 77.8% 大学教育に取り入れる必要性が高いと判断されたのは、一般の文章を読む、書くという項目で、英会話を若干ではあるが上回った。職種によって差が大きいのは専門的文書の読み書きとプレゼンテーションの項目で、専門的文書の読み書きは技術職、研究職のグループが事務職、営業職のグループよりもはっきりと必要性が高いことが現れている。またプレゼンテーションについて事務職はそれほど必要としないものの、技術職、研究職に加え営業職も4割を超える数字となっており、英語できちんと発表する能力が求められていることが伺える。
- 入社・昇進の際の英語力重要度
企業に入社する際や昇進の際にどの程度英語力が重視されるかを調査した。入社試験に英語の試験があるとの回答は55.6%であった。しかし昇進の際に重視するかについては、次のような回答であった。
大変重視する 重視する ある程度重視する 参考まで 8.9% 8.9% 11.1% 48.9% この結果からは入社時には選抜のために英語の試験を課すものの、昇進の際には参考程度というところが多いことが分かった。このことは吉田(2003) に「一般の企業では、新卒採用時には個人の人間性が重視され、即戦力としての英語力はそれほど必要とされていない。むしろ、入社後、英語力が求められる場合が多い。」とされていることと異なる結果となっている。ただしこれは今回の調査対象で回答を得た企業における状況であり、一般化するにはさらに多くの調査が求められる。
- 大学の英語授業で役立ったこと
役立った大学の英語授業について自由記述で回答を得た。まず「英詩」という回答があった。理由として、大学でしか専門的に学べない分野であり、古いが文体が美しいというコメントがあり、企業での実務とは切り離して大学での英語教育のめざす理念を理解しているかの意見である。これ以外は「社会問題に関するディベート」「ネイティブスピーカーによる授業」「英語プレゼンテーション」「スピーチクラス」のように実際に英語を使いながら学ぶ発信型の英語授業が役立ったとするものが多く、内容としては「時事英語」「CNNで英語を学ぶ」などのように、社会の動向に興味を向けさせるような授業が役立ったという意見がみられた。また「リスニングの授業」は聞く力がついてTOEICの得点の向上につながったというコメントがあった。
大学における英語教育が英語の総合力を高めるために4技能をバランスよく伸ばすものであることが望ましいが、社会に通じる役に立つ英語も視野に入れた指導も同時に期待されるところである。
- 大学の英語授業に望むこと
大学の英語授業に対して期待することについても自由記述による回答を得た。英語ができるということと仕事ができるということが直結するわけではないが、仕事の幅が広がることも事実であるという意見があり、仕事上、英語が必要かどうかに関わらず、大卒者にはある程度英語を使える力が期待されていることが伺える。しかし一方で大卒でも英会話ができないという事実の指摘もある。回答に記載された大学の英語授業に望む具体的な内容として、英文メールやビジネスレターの基本的な書き方の学習、英語の音に耳で慣れること、英語でプレゼンテーションができるようにすること、英語による簡単なマニュアルが読みこなせること、日系の会社でも外国人と接する機会があるので基本的な英会話、読解力、文章力がつくようにすることと、といったようにビジネス英語やコミュニケーション能力の訓練をぜひ取り入れてほしいというものが多くみられた。前述の吉田(2003)も外資系企業では即戦力としての英語力のある人材が求められており、学校で習う英語は通用せず、丁々発止とわたりあう英語交渉力が必要と述べている。
しかし企業の現場では大卒新入社員に接する中で、単にスキルの向上に焦点を当てた大学英語教育を危惧する声もある。例えば、職に有利なように資格取得のみをして人間の内実が伴っていない、TOEIC高得点の人が英語を話せるわけではない、学生の知的レベルが低い、人格の幅を広げるために海外の文化や言語を学ぶという意識を、といった声や、自分の意見を自由に表現できるように、筋道を立てて思考し、論じることができる表現能力を、英語よりも日本語教育の方が重要といった意見もみられた。片言の旅行会話程度を学んでも結局業務上は何の役にも立たないという厳しい指摘もある。
外国語大学のように英語を専門とする大学の英語教育に対する要望としては、英語に関わる文化や経済歴史などを学ぶための手段として英語を習得する場所であってほしいというスキルに偏らないバランスのよい教育を期待する意見と共に、やはり外国語大学ではビジネスコミュニケーションに耐えうるだけの外国語を身につけさせてほしいという期待もみられた。
- 報告書まとめ
今回の調査結果からは、企業で英語を使う頻度は予想以上に低く、昇進にはあまり英語力は問われないが、まず入社するためには、英語力が必要であることが浮かび上がった。企業からの大学英語教育への要望も多く、これらの意見を参考にして大学における英語教育を高等教育としての質を確保しながらも、同時に実践的な運用能力向上を目指した科目を強化し社会の要望に合うように充実させていけば、企業の求める「人格的にもバランスのとれた」「英語を使って仕事ができる」人材を多く企業に送り込むことができるのではないだろうか。
さらに詳細な研究成果発表は、神戸市外国語大学の公開講座の一環(20年7月の予定)として行う予定である。
Strict Standards: Non-static method CCalendar::GetCalendar() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CHtmlBuilder.php on line 217
Strict Standards: Non-static method CCalendar::GetWeekday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 129
Strict Standards: Non-static method CCalendar::GetMonthDays() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 130
Strict Standards: Non-static method CCalendar::GetMonthDays() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 131
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
カレンダー
阪神淡路大震災資料集
加盟大学

UNITY(Academic Community Hall)
Kobe Academic Park Association for the Promotion of Inter-University Research and Exchange
Copyright © 1994 - 2025 UNITY. All Rights Reserved. -- このサイトについて
This page is produced by Kobe City College of Technology.