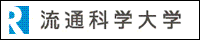共同研究
地域社会における情報発信の未来像
研究者一覧
| 研究者 | 所属大学 | |
|---|---|---|
| 代表者 | 森下 明彦 教授 | 神戸芸術工科大学 先端芸術学部 造形表現学科 |
| 小無 啓司 教授 | 流通科学大学 商学部 経営学科 | |
研究発表テーマ
地域社会における情報発信の未来像
研究概要
- 研究の発端
神戸市・三宮のセンター街という都市の中心に位置する商店街に設置された、大形映像ディスプレイ。それからの映像発信は、様々な可能性を持っていると予想される。商店街のPR活動はもちろん、三宮地域や神戸市における広報、あるいは、地震などの災害情報の提供、など。
こうした映像ディスプレイをどのようなものと捉えるかは、設置の目的に応じて変化するであろう。既に三宮1丁目商店街振興組合の依頼により、本研究の分担者である流通科学大学の小無啓司教授が各商店の宣伝を中心に、神戸空港開設時の商店街キャンペーンなどを発信してきた(私が担当する神戸芸術工科大学ゼミ生も、いわゆるステーションIDの制作や、ディスプレイの名称やロゴマークの作成に関して、わずかであったが、協力させていただいた)。とはいえ、後述するが、私はこの映像装置を公共のテレビのようなものであれば面白いと想像していた。
このような経緯を受け、本研究はこのディスプレイにより、実際に映像上映実験を行う中から、ノウ・ハウを蓄積し、近い将来での映像情報発信のための土台整備を行うという基礎研究を当初の目的にしていた。
- 試行プロジェクト
2005年冬、恒例となった「神戸ルミナリエ」に関連させて、本研究の一環として、この大形映像ディスプレイを活用する市民参加型のプロジェクトを学生と計画し、商店街振興組合に提案した。「ルミナート・プロジェクト」と名付けられたこの試みは、「神戸ルミナリエ」を見に来られた方々に携帯電話に装備されたカメラで「ルミナリエ」を撮影し、その画像を送付していただき、プロジェクト・チームがまとめて加工・編集し、ディスプレイに上映するというものであった。イヴェントという特殊な条件下ではあるが、市民参加による情報発信をねらいとし、将来的には市民/住民による情報提供や発信を可能にしたいと思ってのことであった。
もちろん、実施準備期間が短く、多くの来場者に告知し、写真を送付していただくことも困難であったので、まずは、体制作りとノウ・ハウの取得を目的とした、友人たちなどの協力者に限定した試行と位置付けた(つまり、翌年以降への基礎作りを主眼としていた)。
結果は技術的な問題を克服できず、試作的映像を数回ディスプレイから発信しただけで、プロジェクトを中止せざるをえなかった(商店街新興会の方々、および、小無教授には再度お詫び申し上げたい)。
この試行プロジェクトの後、私はもう一度原点にもどり、情報発信とは何か、あるいは、それと同じようでいて全く異なった性格のアート表現との違いはどこにあるか――という問題を考察しなくてはならないと痛切に思った。なぜなら、市民参加による情報発信も、究極的には個人の表現の最たるものであるアートと何かを共有しているはずだと予想するからであった。さらに、センター街という現実の場所に設置されたディスプレイからは、やはり、地域に根ざした情報が望まれるのであり、再度、この地域性について振り返るべきとも考えた。
- 松本俊夫の仕事
松本俊夫(1932年~)は、我国を代表する映像作家の一人で、1950年代から記録映画、劇映画、そして、実験映画やビデオアートなど、多くのジャンルを越境しながら、新たな表現の世界を切り開いてきたパイオニアである。
この松本のこれまでの歩みを辿る中で、映像表現の根本的な意味を発見できるのではないかと考える。たまたま川崎市市民ミュージアムで開催された「松本俊夫:『映像』の変革」(2006年10月。さらに、主としてビデオ作品を集めた、「眩暈の装置」〔同ミュージアム/2006年9月~11月〕)は、おそらく規模的に未曾有の回顧展であった。
松本の仕事の全貌をここで議論するのは場違いであるが、少なくとも本研究に関して、次の点を取り上げておきたい(他に関連することでは、大人数での制作という、映画特有の集団性とともに、松本が何ゆえに個人制作の実験映画やビデオアートにも取り組んだか、という問題があるが、ここでは省略したい)。それは、『西陣』(1961年/26分)の制作体制に関わるものである。この作品は、1955年に発足し、以来映画上映を続けてきた京都市の観客団体「記録映画を見る会」が企画した。作品観賞を超えて、自らが欲する質の高い作品を自らが、それも運動として、制作するという主旨では、おそらくこの国では最初であったろう。結果的には出来上がった作品に加え、京都市や西陣織物業界の期待(ありふれた教育映画)にかなうようなもう1本と併存となった。だが、今日、 DVD化されるほどに歴史に残っていったのは、前者の、松本俊夫作品であった。
ここで私が感じることは、誰か、すぐれた作家に制作を代替してもらうという運動の中で、いわば一体化を夢見た制作側と受け手側との、なお埋めがたい構造的な溝である。映画制作が特殊な機材と技術を持った専門家にしか可能でなかった時代とは違い、一般に普及した簡便な機材を使えば、ほぼ誰にでも映像制作が行なえる現代においても、未だこの溝が存在することに留意すべきであろう。より一層、「自分で作る」ということの意味が吟味されなくてはならない。要するに、間接性/直接性の問題である。
- 住民ディレクター
さて、本研究の出発点となったものは、アメリカなどで実践されている、「パブリック・アクセス」による(主としてケーブル)テレビ放送であった。毎日家庭に届くテレビ番組の一部を、NPOなどが企画から制作、放映までを援助しながら、一般市民に開放する。残念ながら日本においては、わずかな例外をのぞき、行われていない。メディアへのアクセス権が余り認知されていないからであろう。
テレビへの「パブリック・アクセス」が諸処の理由でこの日本で実現困難であるとするなら、それに替わりうる別の回路が必要と私は思っていた。つまり、あの大形映像ディスプレイを、「パブリック・アクセス」の場として利用したらどうかと漠然と考えていた。ところが、上述したように、市民参加型のプロジェクトの試行の失敗を反省する中から、もう一度この「パブリック・アクセス」について問題を整理していった。その時、各地での新しい動向を担う方々が集う、「市民メディアサミット」のことを知った。
2006年9月、横浜市で開催された第4回「市民メディアサミット06(正式名称は、市民メディア全国交流集会@よこはま06)」は、「市民メディアは社会をつなぐ」というテーマであった。全体的印象として、未だ大きな力にはなりえてないが、それでも、この国におけるメディアの活用に関する新たな可能性とある種の成熟が感じられた。特に、熊本県球磨郡山江村において、過去10年以上に渡って行ってきた「住民ディレクター」が興味を惹いた。メディアの受け手から作り手へ、といった図式を超えたものであり、個人としての住民による映像情報の制作と発信が、見事に地域と密接に関わった形で実現されていた。
本研究がこれまで抱えていた困難を解決する示唆を得ようと、2006年12月、山江村を訪問し、村会議員の松本佳久氏を始めとする住民ディレクターの皆さんと村役場企画情報センターの方々から話をうかがった。
1991年、熊本のテレビ局のプロデューサーであった岸本晃が、地域づくりの番組企画を村に持ち込んだ。村民が主役となった「住民の政策参画番組」(当時の村役場の担当で、現村長の内山慶治の表現)であった。数カ月に及んだ準備を経て実現した祭と、その経過を収録した番組はともに成功した。その後、フリーとなった岸本はあるケーブルテレビ局に「パブリック・アクセス」枠を確保し、山江村も含む熊本県内からの情報を放映した。山江村からは先述の松本佳久が、稲作りや災害の模様を方言丸出しで田んぼから映像を送っていた。
こういった経緯で山江村に「住民ディレクター」が誕生し、今では全国各所に続々と輩出している。「市民メディアサミット」においては、それを「番組制作を通じて企画力を高め、自分自身の生き方や地域、社会のあり方を考える活動」と説明していた。
期せずして育ての親となった岸本晃の考え方の興味深い点は、映像制作技術よりも生活感覚の重視にある。彼は、「はっきりいえば、主観の映像化が魅力であり、武器だ」という(まったく個人的で「多くの人に共通するテーマがみえ」ないのは問題となろうが)。そして、「住民ディレクター」といえども、「発信者みずから責任をもつのが大原則」なのである。こうした思考は、当然ながら、マスメディアであるテレビとは異なるものであり、独自なものといえる。しかし、今回の報告では議論する余裕がないが、先に見た、ジャンルを横断していった松本俊夫が体現する、アートとしての個人表現と比較してみることは必要であろう。
山江村の住民ディレクターが集まり、「マロンてれび」という組織を立ち上げたのが、2001年。現在では独自な活動が全国的に注目され、先に述べた「市民メディアサミット」の第3回が開催された(2005年)ほか、情報ツーリズムとして、多くの見学者が訪れているという。
- まとめ
かくして、市民自身が情報を発信する可能性と意義が少しは明瞭になってきたのではないだろうか。とはいえ、本研究の結論は、何も山江村でのような「住民ディレクター」を早急に養成して、三宮センター街の大形映像ディスプレイ(名称の「ブルー・オーシャン・ステーション」、略して、「BOS」)からの情報発信を担ってもらおうと提案するものではない。このディスプレイには、山江村の場合と比較すると、多くの相違点が付帯するからである。技術的なこともあれば(たとえば、ディスプレイの立地場所に由来する、ある程度の長さ以上の映像作品を見続けることの困難さ、スピーカーからの音量の問題、など)、もっと本質的なこともある(コミュニティ意識の違い、など)。
映像メディアではないが、既に、インターネットにおけるサイト開設やブログからの発信が盛んになってきている。あるいは、ごく最近のものでは、投稿映像を専門にするサイト(たとえば、「YouTube」、など)がある。市民個人からの情報発信は現代では誠に簡単に可能となり、その限り、もはや以前望まれていた「パブリック・アクセス」が実現してしまったと考える向きもあるだろう。しかし、はたしてそうであろうか?
これはインターネットの特性であるが、ネットにつながっている限り、地域は問われないのである。この点は長所でもあり、短所でもありうる。だが、三宮センター街に設置された大形映像ディスプレイは、自ずとその設置場所を背負ったものである。地域性を抹消することは出来ないのである。他方、山江村の「住民ディレクター」が制作した映像番組は、2003年以来「山江村民テレビ」という名称でインターネットで公開されているにしても(他に、不定期に各地のケーブル局などで放映されている)、そこには山江村という地域が明白な仕方で顔を見せている。
この研究でキーワードとしていた「直接性」とは、あることに関わる市民みずからが情報を発信するという意味でもあるが、同時に、その市民が日々暮らす地域に直接つながっているということでもある。
このような二重の「直接性」を背景に持った地域住民による映像制作は、既存のメディアが必然的に抱え込んでしまう諸問題(作り手と取材対象のヒエラルキー、伝えたい情報と伝わった情報との相違、事実と再現の境界の曖昧さ、などなど)を基本的に回避できる。その限り、そのような実践は、メディアに対する優れた批判ともなりうるのである。
要約するなら、望まれる情報発信とは、地域に深く根ざし、自発的な思いにかられた(つまり、二重の意味での「直接性」をまとった)、発信への責任を担える生活者による、いわばアート的で主観的な「情報表現」となるであろう。これは、三宮センター街の大形映像ディスプレイに関しても適用できるのではないか、ということである。さらには、このディスプレイから映像情報を発信する際、是非そうした情報表現者に活躍していただきたいと願う。
- 附記:
熊本県球磨郡山江村での調査に当り、文中でも記しましたが、多くの方々にご協力をいただきました。また、映像ディスプレイを設置する三宮1丁目商店街振興組合の皆様にも試行プロジェクトやその他の件で、お世話になりました。感謝の意を表します。
- 参考文献:
- 浅井栄一「完成した二本の映画――『西陣』をめぐる諸問題――」(「記録映画」1962年2月号/記録映 画作家協会)
- 『松本俊夫実験映像集DVD-BOX』(2005年/デックスエンタテインメント)
- 津田正夫/平塚千尋編『パブリック・アクセスを学ぶ人のために』(世界思想社/2002年)
文中引用した岸本晃の「IT時代の『紫式部』と『國創り』――行動する熊本の住民ディレクター――」を含む。
- 内山慶治/松本佳久「住民主体の情報発信による地域コミュニティの形成――熊本県山江村住民ディレクター『つれづれ記』――」(『コミュニティ政策 4』2006年/東信堂)
- 関連サイト:
- 「やまえ村民テレビ」サイト:http://www.ystv.jp/
Strict Standards: Non-static method CCalendar::GetCalendar() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CHtmlBuilder.php on line 217
Strict Standards: Non-static method CCalendar::GetWeekday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 129
Strict Standards: Non-static method CCalendar::GetMonthDays() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 130
Strict Standards: Non-static method CCalendar::GetMonthDays() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 131
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
カレンダー
阪神淡路大震災資料集
加盟大学

UNITY(Academic Community Hall)
Kobe Academic Park Association for the Promotion of Inter-University Research and Exchange
Copyright © 1994 - 2025 UNITY. All Rights Reserved. -- このサイトについて
This page is produced by Kobe City College of Technology.