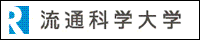共同研究
高齢化と人口減少局面における郊外住宅地の抱える問題の分析と対策
研究者一覧
| 研究者 | 所属大学 | |
|---|---|---|
| 代表者 | 植野 和文 教授 | 兵庫県立大学経済学部 |
| 和田 真理子 助教授 | 兵庫県立大学経済学部 | |
| 上瀬 昭司 助教授 | 兵庫県立大学経営学部 | |
| 森田 二朗 教授 | 神戸市立工業高等専門学校電気工学科 | |
研究発表テーマ
高齢化と人口減少局面における郊外住宅地の抱える問題の分析と対策
研究概要
- 地下鉄西神中央駅直近マンションの調査結果
- 西神ニュータウン内からの移住が3割近くあり、ニュータウン内で人口の移動が生じている。特に戸建からの移住が3割あり、従来からの戸建志向に変化が見られる。
- 移住の動機では駅、医療・商業施設に近い事、つまり利便性が非常に重視され、移住後の居住環境の評価でも買い物、公共交通機関、道路、通学・通勤、都心へのアクセスなど利便性に対する満足感が高い。
- 歩道や緑道の起伏が少ない点でも満足感が高く、高齢社会の一面が垣間見られる。
- 地域活動に対する満足度は低いが、この理由として活動が少ないためなのか、今の活動に魅力がないかないしは居住年数が短いためなのか、さらに調査を要する。
- 移住の重要な理由の一つに防犯体制の充実があり、治安が住宅地選好に影響している。
- 買い物などの活動では地下鉄が大きな役割を果たしており、生活圏が地下鉄沿線から都心にかけて形成されている。そのため自家用車のない世帯が2割程度ある。
- 住みよさの評価が非常に高く、理想とするライフスタイルを実践している人が多い。そして永住希望者も6割とマンションとしては高率であり、ここにも戸建志向に変化が見られる。
- 買い物はほとんどが西神中央で、残りは地下鉄沿線の商業施設であるが、宅配や共同購入など配送サービスの利用も1割を超えている。買い物の交通手段は西神中央なら徒歩、地下鉄沿線なら自家用車と地下鉄である。
- 外出先とその頻度では、マンション近辺やニュータウン内が多いが、都心や地下鉄沿線にも週一回程度出かけるという地下鉄依存型のライフスタイルが成立している。
- 福祉パスの利用によって生活圏が広がり、親戚・知人・友人らとの人間関係も一層充実している。この制度が福祉サービスや交流による地域活性化の視点で評価すべきことを示唆する。
- 戸建住宅街(桜ヶ丘)の調査結果
- 移住理由として、不動産価格の手頃感、自然環境の豊かさ、街並みが重視されている。
- 居住年数が20年を越える世帯が6割近くあり、夫婦だけの世帯が4割弱、それに1人暮らしが1割程度と街全体の高齢化が進んでいる。
- 地域活動への参加はあまり活発ではないが、人間関係は家族、近所の人を中心に幅広い。
- 子供夫婦との同居は1割程度に過ぎないが、6割程度の人が月一回以上の頻度で往来がある。また二世帯住宅も少なくない。
- 買い物では西神中央への依存が強いこと、宅配や共同購入など配送サービスの利用が多いことが特徴である。
- 生活圏は当該住宅街を中心にしながら、外出頻度の高い西神中央に広がっている。理想とするライフスタイルは概ね実践されている。
- 居住環境の評価は余暇活動、通勤・通学、公共交通機関の便、都心へのアクセスなどに不満が多く、都心へアクセス、医療・福祉サービス、治安、買い物の利便性、公共交通サービスが重視されている。ここでも治安の重視が目立つ。
- 本研究の成果は2005年3月刊行の『商大論集』(第56巻第4号)で発表。
Strict Standards: Non-static method CCalendar::GetCalendar() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CHtmlBuilder.php on line 217
Strict Standards: Non-static method CCalendar::GetWeekday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 129
Strict Standards: Non-static method CCalendar::GetMonthDays() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 130
Strict Standards: Non-static method CCalendar::GetMonthDays() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 131
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
Strict Standards: Non-static method CCalendar::IsHoliday() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/home/aa160ypjcg/html/php/CCalendar.php on line 141
カレンダー
阪神淡路大震災資料集
加盟大学

UNITY(Academic Community Hall)
Kobe Academic Park Association for the Promotion of Inter-University Research and Exchange
Copyright © 1994 - 2025 UNITY. All Rights Reserved. -- このサイトについて
This page is produced by Kobe City College of Technology.